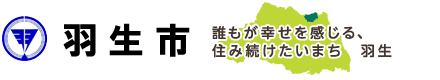公開日 2015年02月25日
更新日 2024年10月24日
国民年金の給付
年金請求手続きはご自身で
年金は、一定の年齢に達した場合等により受給資格が得られたとしても、ご自身で年金の請求手続きをして初めて受給できます。
請求先と必要書類は、請求する年金の種類や今まで加入した年金の種類により異なりますので、請求前にご確認ください。
年金振込日
年金の振込は、偶数月の15日(15日が金融機関の休業日の場合、前営業日)に行われます。
請求をしてから初めて支給される年金は奇数月に振り込まれることもあります。
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、国民年金保険料を10年(120月)以上納めた人が、65歳に達した場合に支給されます。
手続場所
1. 国民年金第1号被保険者期間のみの方
- 市役所(国保年金課)または年金事務所
65歳になり請求をする場合、65歳の誕生日の前日以降に手続ができるようになります。その日以前は手続きができませんのでご注意ください。なお、繰上げ請求や繰下げ請求をすることもできます。
- 受給金額について確認されたい場合は、年金事務所へご相談ください。
2.厚生年金期間や第3号被保険者期間がある方
- 年金事務所
障害基礎年金
国民年金加入中や20歳前に初診日のある病気やけがで障害の状態になった場合、障害基礎年金を受けることができます。障害基礎年金を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。
詳しい内容は、日本年金機構のホームページも確認してください。
障害基礎年金を受給するための要件
| 要 件 | 内 容 |
| 初診日 |
該当する病気やけがで、初めに医療機関を受診した日付が、次のいずれかの期間であること
|
| 障害の程度 | 障害認定日において年金法で定める1級または2級の障害の状態であること |
| 保険料納付要件 |
次のどちらかを満たすこと
※20歳前傷病の場合、納付要件はありません。 |
| 障害認定日 |
|
※ 初診日とは、「当該する病気やけがに関連して初めて医師の診療を受けた日」のことです。
※ 障害年金の障害等級は、年金法上の基準により決定します。障害者手帳の等級と同じではありません。
手続場所
※ 手続場所は、初診日のときに加入していた年金制度により異なります。
1.初診日が国民年金第1号加入中、または20歳前のとき
市役所(国保年金課)、または年金事務所
2.初診日に厚生年金加入中のとき
年金事務所(障害厚生年金の対象となります。)
3.初診日に共済年金加入中のとき
各共済組合(障害共済年金の対象となります。)
4.初診日に第3号加入中のとき
年金事務所
遺族基礎年金
国民年金の被保険者期間中等に死亡したとき、その方が一定の要件を満たしている場合には、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に遺族基礎年金が支給されます。
遺族基礎年金を受給するための要件
死亡した方の要件
死亡した方について、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
- 国民年金に加入している人
- 加入を終えた後でも60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる人
- 資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受けている人
- 老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある人
ただし、1と2の場合、死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの国民年金に加入しなければならない期間のうち、3分の2以上の期間が、保険料を納めた期間または保険料を免除された期間のいずれかであるという保険料納付要件を満たすことが必要です。
また、3分の2の条件を満たせなくとも、令和8年4月1日前に65歳未満の死亡日があるときには、死亡日の前日において、死亡日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ遺族基礎年金が支給されます。
支給を受けられる方の要件
死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた以下の方が対象となります。
- 子のある配偶者
- 子
※子:18歳になった年度の3月31日までの間にあること。20歳未満で障害等級1級2級の障害の状態にあること。婚姻していないこと。
手続場所
※ 手続場所は、死亡時に加入していた年金制度により異なります。
1.死亡時に国民年金第1号加入中だったとき
市役所(国保年金課)、または年金事務所
2.死亡時に厚生年金加入中のとき
年金事務所(遺族厚生年金の対象となります。)
3.死亡時に共済年金加入中のとき
各共済組合(遺族共済年金の対象となります。)
4.死亡時に国民年金第3号加入中のとき
年金事務所
※ 老齢厚生・老齢基礎・遺族厚生・障害厚生年金の受給者が死亡したときの未支給年金の手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。
寡婦年金
寡婦年金は、第1号被保険者としての納付期間、免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡した場合、その夫と婚姻関係があった妻に対し60歳から65歳になるまで支給されます。
寡婦年金を受けられる要件
亡くなった夫の要件
- 保険料納付済期間と免除期間(学生納付特例、若年者納付猶予を除く)だけで10年以上あること
- 障害基礎年金や老齢基礎年金を受給したことがないこと
妻の要件
- 死亡した夫に生計を維持されていたこと
- 婚姻関係が10年以上継続していたこと
- 自身が65歳未満であり、老齢基礎年金を繰上げ請求していないこと
寡婦年金の年金額
- 夫の老齢基礎年金額の4分の3に相当する額
手続場所
市役所(国保年金課)または年金事務所
※死亡一時金にも該当する場合、寡婦年金と死亡一時金は受給選択になります。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付された方が亡くなられ、遺族基礎年金を受けられない場合、遺族に支給されます。
死亡一時金を受給するための要件
死亡した方の要件
・国民年金第1号被保険者期間の保険料が、36月以上あるとき
・老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないとき
支給を受けられる方の要件
死亡した人の死亡当時、その人によって生計を維持されていた方のうち、以下の順位による上位者が対象となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
死亡一時金の支給額
死亡一時金の支給額は、第1号被保険者期間の国民年金保険料を納めた期間に応じて決まっています。
| 納付期間 | 金額 |
|---|---|
| 3年以上15年未満 | 120,000円 |
| 15年以上20年未満 | 145,000円 |
| 20年以上25年未満 | 170,000円 |
| 25年以上30年未満 | 220,000円 |
| 30年以上35年未満 | 270,000円 |
|
35年以上 |
320,000円 |
※一部免除期間の保険料納付がある場合、その免除区分に応じて計算した月を納付月数に含めることができます。全額免除
期間については含めません。また付加保険料納付済期間が3年以上の場合は、支給額に8,500円が加算されます。
手続場所
市役所(国保年金課)または年金事務所
未支給請求
年金の支給を受けていた方が亡くなった場合、年金は亡くなった月まで支給されます。
その際、死亡した方と生計を同じくしていた遺族が、未支給年金としてその年金を受けることができます。
支給を受けられる方
死亡者の死亡当時、生計が同一であった以下の順位による遺族となります。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- 上記以外の三親等内の親族(甥、姪、子の配偶者、叔父叔母、曾孫、曾祖父母等)
手続場所
手続場所は、受給していた年金の種類により異なります。
| 手続場所 | 受給されていた年金の種類 |
| 年金事務所 | 老齢厚生年金・旧法国民年金・障害厚生年金・遺族厚生年金 |
| 市役所・年金事務所 | 老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金 |
| 各共済組合 | 退職共済年金・障害共済年金・遺族共済年金 |
※受給者が死亡した時の未支給年金の手続きについては、年金事務所へお問い合わせください。。