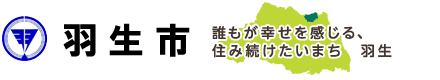公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月01日
ムジナモって何(なに)?

羽生市のキャラクター“ムジナもん”の名前(なまえ)の由来(ゆらい)にもなった「ムジナモ」は、食虫植物(しょくちゅうしょくぶつ)です。
ムジナ(アナグマ)のシッポに似(に)ていることから、その名(な)がつけられました。

ムジナモは光合成(こうごうせい)のほか、ミジンコなどを葉(は)っぱの先端(せんたん)でつかまえて栄養(えいよう)にします。葉(は)っぱが閉(と)じるスピードは、なんと0.02秒(びょう)!植物界(しょくぶつかい)では最速(さいそく)と言(い)われています
ムジナモの一年(ねん)

| 時期(じき) | 内容(ないよう) |
| 3月(がつ)~4月(がつ) | 気温(きおん)が上(あ)がるとムジナモが水面(すいめん)に浮(う)かびあがります。 |
| 5月(がつ)~10月(がつ) | ムジナモが分(わ)かれて増(ふ)えて、成長(せいちょう)します。 |
| 7月(がつ)~8月(がつ) | 花(はな)が咲(さ)くことがあります。 |
| 11月(がつ) | 冬芽(とうが)※の準備(じゅんび) |
| 12月(がつ) | 冬芽(とうが)となって水底(みずぞこ)に沈(しず)みます。 |
※冬芽(とうが):冬(ふゆ)を越(こ)すために、芽(め)に栄養(えいよう)を集(あつ)めます。茎(くき)や葉(は)がなくなり、芽(め)だけになります。
ムジナモの花(はな)

ムジナモは、分岐(ぶんき)して増殖(ぞうしょく)する植物(しょくぶつ)ですが、まれに花(はな)を咲(さ)かせることがあります。ムジナモの花(はな)は真夏(まなつ)のよく晴(は)れた日(ひ)のお昼(ひる)頃(ごろ)にしか咲(さ)きません。しかも、開花(かいか)時間(じかん)はわずかに1時間(じかん)ほど!そのため、“まぼろしの花(はな)”と言(い)われています。
宝蔵寺沼(ほうぞうじぬま)ムジナモ自生地(じせいち)

羽生市三田ヶ谷(みたかや)に「宝蔵寺沼(ほうぞうじぬま)ムジナモ自生地(じせいち)」があります。宝蔵寺沼(ほうぞうじぬま)ムジナモ自生地(じせいち)は国(くに)の天然記念物(てんねんきねんぶつ)に指定(してい)されています。
現在(げんざい)、開発(かいはつ)により自生地(じせいち)がなくなったり、ほかの生物(せいぶつ)による食害(しょくがい)などによってムジナモは絶滅(ぜつめつ)の危機(きき)にあります。
羽生市教育委員会(きょういくいいんかい)では自生地内(じせいちない)の草(くさ)を刈(か)ったり、ムジナモを食(た)べる生物(せいぶつ)を捕獲(ほかく)するなどいろいろな団体(だんたい)と協力(きょうりょく)し、ムジナモを守(まも)る活動(かつどう)をしています。
ムジナモを日本(にほん)で初(はじ)めて発見(はっけん)! 牧野 富太郎(まきの とみたろう)
1890年(ねん)、牧野富太郎(まきのとみたろう)博士(はくし)が東京都内(とうきょうとない)にある江戸川区(えどがわく)に行き、不思議(ふしぎな)な草(くさ)を見(み)つけました。ムジナモが日本(にほん)で初(はじ)めて見(み)つかった瞬間(しゅんかん)でした。
日本(にほん)でムジナモを初(はじ)めて発見(はっけん)した牧野富太郎(まきのとみたろう)博士(はくし)ですが、宝蔵寺沼(ほうぞうじぬま)ムジナモ自生地(じせいち)を訪(おとず)れた記録(きろく)はありません。「もしも牧野博士(まきのはくし)が宝蔵寺沼(ほうぞうじぬま)ムジナモ自生地(じせいち)でムジナモを発見(はっけん)したら」というコンセプトで画像(がぞう)を作成(さくせい)しました。