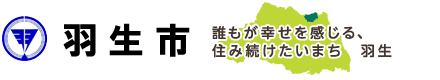公開日 2015年02月25日
更新日 2024年03月01日
介護サービスの利用には、まず高齢介護課の窓口で要介護認定の申請が必要です。
利用条件
要介護状態・要支援状態になったとき
- 第1号被保険者
a) 要介護者(寝たきり・認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常生活動作に常に介護が必要な人)
b) 要支援者(家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態の人) - 第2号被保険者
・ 特定疾病(初老期認知症、脳血管疾患、パーキンソン病、末期がん等)による要介護者・要支援者
介護サービスを受けるまでの流れ
介護保険サービスを利用するには、まず要介護(要支援)認定を受ける必要があります。
※総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」については、このリンクまたはページ下部にある、関連記事から参照してください。
(1)申請
高齢介護課介護保険係の窓口で、本人または家族が行うことができます。
(2)主治医意見書
市の依頼により主治医が意見書を作成します。
(3)訪問調査
認定調査員がご自宅等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
(4)審査
訪問調査の結果や主治医意見書をもとに審査を行います。
(5)認定・通知
認定結果は、申請から原則30日以内で通知されます。
要介護度に応じて、利用できるサービスや月々の利用限度額などが違います。
(6)介護サービス計画書の作成
介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画書の作成を行います。
「要支援1」「要支援2」の認定が出た方→お住まいの地区の地域包括支援センターに相談してください。
「要介護1」以上の認定が出た方→居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)に依頼してください。
羽生市の地域包括支援センターのご案内
羽生市内の居宅介護支援事業者の一覧はこちらです
指定居宅介護支援事業者一覧(R6.3.1現在)[PDF:91.2KB]
(7)介護サービス利用開始
羽生市内の介護サービス事業所の一覧はこちらです
市内介護サービス事業者一覧(R6.3.1現在)[PDF:145KB]
≪介護保険制度パンフレット≫
介護保険制度パンフレット(R4.4月制度改正対応版)[PDF:6.53MB]
サービスの種類
※サービス内容をクリックすると、厚生労働省の管轄するウェブサイトにリンクします。
居宅サービス
施設サービス
地域密着型サービス
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
介護保険サービスの利用料
介護保険のサービスを利用した時は、原則として利用料の1割、2割又は3割を支払います。
この割合は、要介護(要支援)認定を受けている方に発行している、ピンク色の負担割合証に記載されています。
| 所得区分 | 自己負担割合 | ||
|
右の(1)(2)の両方を満たす方 |
(1)65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 (2)本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が ・本人のみの場合:340万円以上 ・2人以上の場合:合計463万円以上 |
3割 | |
|
右の(1)(2)の両方を満たし、3割負担の対象とならない方 |
(1)65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 (2)本人を含めた同一世帯の65歳以上の方の年金収入+その他の合計所得金額が ・本人のみの場合:280万円以上 ・2人以上の場合:合計346万円以上 |
2割 | |
|
2割負担、3割負担の対象とならない方(64歳以下の方、本人の合計所得金額が160万円未満の方等) |
1割 | ||
居住費・食費の減免制度(特定入所者介護サービス費)
施設入所時にかかる居住費・食費について、所得や預貯金等が一定以下の方の負担が軽減されます。
所得に応じた自己負担の上限(限度額)が設けられており、これを超える利用者負担はありません。入所サービスを受ける月に、窓口で申請をしてください。
その後、対象になる方には負担限度額証を発行します。
対象になる方
1 生活保護受給者、もしくは老齢福祉年金受給者で介護保険の認定を受けている方
2 次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方
(1)市区町村民税非課税世帯に属していて、介護保険の認定を受けている
(2)世帯が分かれている配偶者についても市区町村民税非課税である
(3)預貯金等が本人の収入状況に応じて下表の資産要件以下である
| 利用者負担段階 | 対象者 | |||||||
| 対象となる収入状況 | 預貯金等の資産要件 | |||||||
| 第1段階 | 生活保護・老齢福祉年金受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
||||||
| 第2段階 | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 |
単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
||||||
| 第3段階① | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 |
単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
||||||
| 第3段階② | 本人の年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
||||||
・64歳以下の方は、単身:1,000万円以下(夫婦:2,000万円以下)
※不正があった場合には、ペナルティ(加算金)を設けます。
申請に必要なもの
・被保険者証
・預貯金等の保有資産の内容がわかるもの(例):預貯金・有価証券等の通帳残高、現金預金は自己申告
1日あたりの自己負担限度額
| 所得に応じた区分 | 居住費(滞在費) | 食費 | ||||
|
従来型個室 (老健・療養等) |
従来型個室 (特養等) 短期入所生活介護 |
多床室 | ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
||
|
・生活保護受給者の方 |
490円 | 320円 | 0円 | 820円 | 490円 | 300円 |
|
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
490円 | 420円 | 370円 | 820円 | 490円 |
390円 (600円) |
|
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方 |
1,310円 | 820円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 |
650円 (1,000円) |
|
・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と 課税年金収入額の合計が120万円超の方 |
1,310円 | 820円 | 370円 | 1,310円 | 1,310円 |
1,360円 (1,300円) |
※( )内の金額は、短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の限度額です。
特例減額措置
上記の軽減の対象にならない方のうち、高齢者・夫婦世帯等で一方または両方が施設に入所したために生活困難に陥らないように、入所者の食費・居住費が軽減される特例措置があります。
特例措置の対象者
次の要件を全て満たした方です。
- 属する世帯の構成員の数が2人以上(施設入所により世帯が分かれた場合も、なお同一世帯とみなす。)
- 介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、特定入所者介護サービス費の給付を受けていない
- 全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額と年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。以下同じ。)の合計額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
- 全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
- 全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない
※手続については、高齢介護課へお問い合わせください。
高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの1割または2割の利用者負担(介護保険適用分のみ)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたときは、超えた分が「高額介護サービス費」として後から給付されます。
給付を受けるには市への申請が必要です。対象になる方には、申請書を送付していますので、申請をしてください。
| 区分 | 限度額 | |
|---|---|---|
| 生活保護の受給者の方等 | 15,000円(個人) | |
|
世帯全員が市区町村民税非課税で |
・老齢福祉年金受給者の方 ・前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方等 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 世帯全員が市区町村民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方等 | 24,600円(世帯) | |
|
市区町村民税課税世帯の方で下記区分に該当しない場合 ※介護サービスを長期に利用している方に配慮し、同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービス利用していない方も含む)の利用者負担割合が1割の世帯には、年間上限額(446,400円=37,000円×12か月分)を設定します。 |
44,400円(世帯) | |
|
現役並み所得相当の方がいる世帯の方 ※同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいて、年収が383万円以上の世帯(2人以上いる世帯は520万円以上) |
所得約380万円(年収約770万円)未満 | 44,400円(世帯) |
|
所得約380万円(年収約770万円)以上 所得約690万円(年収約1,160万円)未満 |
93,000円(世帯) | |
| 所得約690万円(年収約1,160万円)以上 | 140,100円(世帯) | |
関連情報
申請書ダウンロード
※両面印刷で作成してください。
居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書[DOCX:20KB]
居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書[PDF:127KB]
※契約終了に伴い、終了届を提出してください。
居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(新規)[DOCX:18KB]
居宅サービス計画等作成依頼終了届出書(新規)[PDF:100KB]
※ 身分証のコピーを同封してください。
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード